
バニシング・メッシュ
2017/02/18(土) 〜 2017/05/14(日)
10:00 〜 19:00
山口情報芸術センター[YCAM]
| 2017/05/04 |
|
山口県山口市にあるアートセンター、山口情報芸術センター[YCAM]はメディア・テクノロジーを用いた新しい表現の探求を軸に活動し、国際的に注目を集めている。多彩なイベントを開催する同館で開催される「Vanishing Mesh(バニシング・メッシュ)」は、現在の情報環境を批評する、問いかけのような展覧会となっている。本記事は、展覧会参加作家サイン・ウェーブ・オーケストラ(SWO)の一員であり、九州大学芸術工学研究院准教授の城一裕氏(以下、J)から、展覧会担当キュレーターでYCAM副館長の阿部一直氏(以下、A)に向けたインタビューとしてはじまった。出展作家と言えば、普通はインタビューを受ける立場。逆転して続く対話が行き着く先は―(編集部)
J:今回の「Vanishing Mesh」展は、”メディア・アートの現在形を意識しつつ、テクノロジーマニアックス自らによるテクノロジー依存症への自己批評性から、ネクストフェイズを探り出していこうとする”、という発想に対する応答から生まれた企画とのことですが、まずここで意識する対象として挙げられている”メディア・アートの現在形”とは、具体的には何を指すのでしょうか。
A:メディア・アートが、どの時点を起源にし、どんな段階を経て、何世代目に来ているかの認識は、様々なアプローチがあり、いまだに定着した一般論はないというのが現状です。それを踏まえると、アーティストサイドにおいて、自らの企てが、どのような時期に当たっているのかを自己申告的に意識し、設定する意義は十分あると考えられます。メディア・アートは特に、その時点時点での更新されるテクノロジーと依存関係があることは明白だからです。
メディア・アートにおけるコミュニケーションやインタラクションの用途への対応の推移を振り返るなら、コンピュータの処理能力(CPU、パラレル処理など)、解像度の進化が、推移をテクノロジー側から規定していることは確かなことです。とりあえず大雑把な視点から、ここ四半世紀を振り返るとすると、まず90年代前半に、とりあえずデザインの一部であったCGという位置づけを覆して、グラフィックボードのリアルタイムの画像生成のインタラクションがコンピュータ処理によって実現可能になった時代が最初のピークと考えられます。そこから、デジタル・コミュニケータやデジタル・インターフェイスとしてのデバイスが一般化されたと言えます。アートはまだ、オブジェクティブなものであるという先入観もあり、それらがイコール、メディア・アートであると見えていた側面があります。次に、MAX MSP(*注1)の登場と普及に代表される、パソコン上で個人ユーザーが簡易に情報デザインできるようになった90年代後半以降〜2000年前後が、第2のピークと考えられるかもしれません。ここでは、メディア・アートは、ソフトウェア・アートやコード・アートの性格が強まります。特に、音響に注目したサウンド・アートがこの点において興隆を極めました。そして現在は、さらに進化したビッグデータ処理以降の、多様な領域に拡張していくコンピューティングの可能性の時代となりました。ビッグデータが、デジタル・ワールドだけでなく、モノの世界や実世界の空間とネットワークにより緻密に繋がることが求められる、共生態というような新たな情報と存在のあり方が基盤となりつつある時代に入ってきたと言えます。
巨視的に見るなら、人間の要求する処理に対してコンピュータが追いついていく開発の時代から、コンピュータによる情報処理が、人間の記憶容量を軽く超え、想像できる処理能力をはるかに超えて、膨大なデジタルアーカイブ、データベースやAIによる学習機能と連動する時代への渦中にあることは確かです。それによって処理領域やプロトコルの同期性の範囲が大幅に変わることでメディア・アートの可能性、および不可能性は、別の段階に入り始めているということができるかと思います。
ここでSWOのメンバーでもある城さんにお聞きしたいのは、テクノロジーから文化を見た場合に、上記に纏めた展開以外に、時代の推移を測れる別の要因やプラットフォームを主張することができるのか、ということです。

J:メディア・アートの時代性を、テクノロジーの変遷、その中でもコンピュータの処理能力、の点から見る、というお答えかと思います。SWOのメンバーの一人としては、”メディア・アートの現在形”をテクノロジーの観点から意識した場合、阿部さんの指摘されたコンピュータの処理能力もさることながら、パーソナル・ファブリケーション(*注2)に代表される機器の製造プロセスの個人化と、プロジェクタのような周辺機器のコモディティ化が挙げられるのではと考えます。これは、前者で言えばSWOのスタジオBでの展示作品《The SINE WAVE ORCHESTRA stay》におけるデバイスの製作であり、後者で言えばスタジオAでの展示作品《A Wave》におけるプロジェクタの投影方法になります。

J:より具体的に言うと、《The SINE WAVE ORCHESTRA stay》では、われわれがデザインしたサイン波を生成するアナログ回路を中国の深圳に発注し、できあがってきた基盤にYCAMのチップマウンタを用いて電子部品を配置した上で、サポートスタッフも交えたわれわれの手作業によって、スピーカを取り付けています。今回の展示では、このプロセスでおよそ1000個のデバイスをつくりました。われわれが活動を始めた2000年頃でも技術的にはできたことかもしれませんが、製造コストを含めたエコシステムは、当時はなく、その意味においてはこのデバイスはある種の同時代性を具現化したものと言えるかもしれません。実際2005年に、NTT ICC(東京)での「Open nature」展に出展した同名の作品でも、無数のサイン波を物理的に実体化するという同種のアイデアはあったものの、当時の環境では予算的にとても現実的ではなく、コンピュータ上で訪れたた人ごとにサイン波を生成するという別種のリアライズをおこなった、という経緯があります。また《A Wave》におけるプロジェクタの投影方法については、2枚のスクリーンによるディフューザーを形作ることによって、高速かつ高精細というプロジェクタならでは特徴、照明では難しい視覚的な表現、であるものの、一方で通常の、特に大規模な投影では、避けることのできないピクセルという格子(メッシュ)の存在を、曖昧なものとすることができたのでは、と考えています。

A:オーディオ/ビジュアル機器のハイスペック化は当然ですが、ものづくりや電子工作のプラットフォームにおいて、例えばArduino(*注3)に代表されるマイコンデバイスとモノや物質的側面との関係性も大いに変化しており、作品を作り出すベースに影響しているということですね。展覧会タイトル「Vanishing Mesh」のメッシュは、当然解像度の細かさに影響を受けるフレームなわけですが、それが非常に緻密になっていくとむしろ、感覚的にはメッシュとは感じなくなるという現象に至ります。それを身体感覚的に消失と考えるのか、あるいはロジカルに消失不可能と捉えるのかの、おおきな分岐を生んでいることになります。《A Wave》では、ソフトウェア的には高解像度で、物質的にはその反対にキアロスクーロなフィルターを設けるという相反したものが結合された知覚をもたらしているという、非常に現在的なアプローチというわけですね。菅野創+やんツーの今回の新作《Avatars》では、高解像度のネット回線を経由して、IoTの一歩先を行き、日常空間のモノたちに視覚的/聴覚的に憑依する、というかハックする、乗っ取るということをあえてやっているわけですが、この憑依感は、VRやARといった完全にカリキュレートされたデジタルなヴィジビリティでは、やはり実感できない世界のデンスのような物質的なヴィジョンの倒錯感をやはり引きつけています。
*注1 音楽とグラフィックを統合して開発することができるプログラミング言語。
*注2 コンピュータやインターネット、3Dプリンターに代表されるデジタルツールを活用し、個人レベルで行なわれるものづくり。
*注3 ハードウェアの設計情報が公開されているマイクロボード。「オープンソースハードウェア」という概念を広める契機となった製品。

2026/01/20(火) 〜 2026/03/15(日)
九州国立博物館

2025/12/13(土) 〜 2026/03/08(日)
福岡市美術館

2026/01/17(土) 〜 2026/03/04(水)
長崎歴史文化博物館

2025/12/02(火) 〜 2026/03/08(日)
TOTOミュージアム
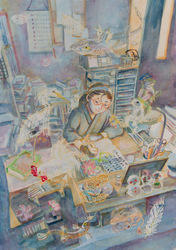
2026/01/04(日) 〜 2026/03/08(日)
熊本市現代美術館